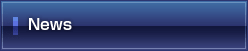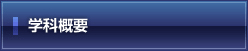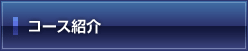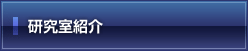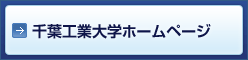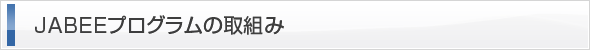- ホーム
- JABEEプログラムの取組み
JABEEプログラムについて(機械設計・開発コースのみ)
JABEEとは
本学科に設置された4コースのうち、機械設計・開発コースは、教育プログラムが実社会の要求に応えるものであり、優れた技術者教育と国際的同等性を確保しているか等について、外部機関に客観的な評価をしてもらうことを前提としたカリキュラムを設定しており、2012年に日本技術者教育認定制度(JABEE:Japan Accreditation Board for Engineering Education)により審査を受け、JABEE認定されました。
この日本技術者教育認定制度とは、大学など高等教育機関で実施されている技術者教育プログラムが、社会の要求水準を満たしているかどうかを公平に評価し、要求水準を満たしている教育プログラムを認定する専門認定制度です。
機械設計・開発コースにおけるカリキュラムは、このJABEEが要請する機械系学生への学習ならびに教育方針を踏襲しており、このコースへの所属を希望する学生は、学科の教育・学習目標とともにJABEEが推奨する理念を充分に理解する必要があります。
機械設計・開発コースへの配属については、学生の希望を優先することを基本方針としています。
機械設計・開発コースへの配属が望ましい学生
機械設計・開発コースは、JABEEプログラムに対応したコースであるため、将来技術者を目指す学生へのカリキュラムが設定されています。技術者とは一般的に「科学上の専門的な技術をもち、それを役立たせることを職業とする人」と定義されています。この定義の冒頭にある「科学上の専門的な技術」とは、機械サイエンス学科における分野では主に物理的な現象を把握するために必要な力学や数学に関する素養を少なからず土台とします。したがって、数学や物理に対して強い嫌悪感や苦手意識を持っている学生には向いていないかもしれません。
また、卒業後、本学科で受けた教育が就職先の業務において役立ったどうか等について意見等を求められる場合があります。すなわち、母校の教育プログラムに対する改善やJABEEの理念に基づいた取り組みに前向きに協力・参加してくれる学生が、機械設計・開発コースへ所属が望ましい学生です。(教員と学生が共に教育プログラム達成に対して努力することを目指しています)
JABEEプログラムのメリット
JABEE認定期間中に本コースを卒業した場合、JABEE プログラムの修了生(本コースを修了した学生)には、次のような利得があります。
- 国際的に通用する技術者として国内外から認められる
- 「修習技術者」となり、「技術士補」として登録できる
- 「技術士」第1次試験が免除される
また、卒業後となりますが、就職先で昇給や昇進という形で優遇される人もいるでしょう。また、大手の企業の中には1次試験を受けることを推奨している場合やJABEE修了生獲得に積極的な企業もあります。特に技術系のコンサルタント会社では、「技術士」の有資格者数でその会社の格付けが評価されます。なお、JABEEと技術士資格の詳細については、以下のホームページを参照してください。
JABEEが定める教育・学習目標
JABEEに準じた教育では、表5-1の(a)~(h)の学習・教育目標を設け、教育・学習の実時間量等について、表5-2のように具体的な数値を掲げています。
表5-1 JABEEが定める教育・学習目標(基準1)
- (a) 地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養
- (b) 技術が社会や自然に及ぼす影響や効果、および技術者が社会に対して負っている責任に関する理解(技術者倫理)
- (c) 数学、自然科学および情報技術に関する知識とそれらを応用できる能力
- (d) 該当する分野の専門技術に関する知識とそれらを問題解決に応用できる能力(別途分野別要件が定められている)
- (e) 種々の科学、技術および情報を利用して社会の要求を解決するためのデザイン能力
- (f) 日本語による論理的な記述力、口頭発表能力、討議等のコミュニケーション能力および国際的に通用するコミュニケーション基礎能力
- (g) 自主的、継続的に学習できる能力
- (h) 与えられた制約の下で計画的に仕事を進め、まとめる能力
表5-2 JABEEが定める学習・教育の量(基準2)
- (1) プログラムは4 年間に相当する学習・教育で構成され、124 単位以上を取得し、学士 の学位を得た者を修了生としていること。
- (2) プログラムは修了に必要な授業時間(授業科目に割り当てられている時間)として、総計1,600時間以上を有していること。その中には、人文科学、社会科学等(語学教育を含む)の授業250時間以上、数学、自然科学、情報技術の授業250時間以上、および専門分野の授業900時間以上を含んでいること。
- (3) プログラムは学生の主体的な学習を促し、十分な自己学習時間を確保するための取り組みを行っていること。
機械および機械関連分野の分野別要件については、表5-3のように3項目が指定されています。また、(d)の第2項目については、表5-4のようにガイドラインが設けられています。
表5-3 (d)の分野別要件(日本機械学会会基準)
修得すべき知識・能力
本プログラムの修了生は、以下の知識・能力を身につけている必要がある。
- (1) 数学については線形代数、微積分学などの応用能力と確率・統計の基礎、および自然科学については物理学の基礎に関する知識。
- (2) 機械工学の基盤分野(材料と構造、運動と振動、エネルギーと流れ、情報と計測・制御、設計と生産・管理)のうち各プログラムが重要と考える分野に関する知識と、それらを問題解決に応用できる能力。
- (3) 実験・プロジェクト等を計画・遂行し、結果を解析し、それを工学的に考察する能力。
表5-4 (d)-(2)の基盤分野とキーワード例
| 基盤分野 | 内容を表すキーワードの例 | 量的ガイドライン |
|---|---|---|
| 材料と構造 | 引張・圧縮・せん断応力とひずみ 弾性と塑性 材料の強度と許容応力 材料の構造と組織 |
左記基盤分野から、プログラムが重要と考える3分野以上について、総計210時間以上の授業時間 |
| 運動と振動 | 静力学 運動の法則 自由振動 強制振動 |
|
| エネルギーと流れ | 状態量と状態変化 質量と運動量の保存 エネルギー保存則(熱力学の第一法則とベルヌーイの式) 熱力学の第二法則 熱移動と温度 |
|
| 情報と計測・制御 | 計算機利用の基礎 計測基礎論と基本的な量の計測法 伝達関数とフィードバック制御 状態方程式と状態フィードバック |
|
| 設計と生産・管理 | 設計法 製図法と規則 加工法 生産・管理システム |